新緑の季節に思うこと
2025年5月6日 弁護士 川原俊明
森に入れば、目には見えない命の息吹を、全身で感じ取ることができる。
動物たちが活発に動き回り、生命の存在を視覚的に体感できる一方で、何の音も立てず、ただ静かに佇む木々や植物たちが、確かに呼吸し、新鮮な酸素を生み出している姿に、私はこの上ない感動を覚える。
彼らの生は、決して目立たない。しかし確かにそこに在り、絶え間なく世界を支えている。
人間は動きに敏感だ。動けば存在に気づき、止まっていれば意識の外に追いやってしまう。
だが本当は、静かに営まれる命ほど、尊いものはないのかもしれない。
木々は騒がず、自己主張せず、ただ存在する。
そして、無償で私たちに酸素を与え、地球を豊かに保ってくれている。
命とは何か。
存在とは何か。
この森の中で、私は改めて生命の神秘に心を震わせた。
人間の歴史——知恵とエゴの狭間で
その一方で、人間の社会に目を向ければ、そこに広がるのは果てしない争いの歴史だ。
文明を発展させ、科学を生み、文化を育んだ人間。
その知恵は、無数の発明や発見をもたらした。
だが、同時に——
欲望も、エゴも、嫉妬も、憎しみも、またこの知恵によって肥大していった。
人間は進化の過程で「知る力」を手に入れた。
それは道具を使い、火を操り、言葉を持ち、社会を築くために必要だった。
しかし、知識の光が強くなるほど、その影もまた濃くなっていった。
己の利を求め、他者を蹴落とし、争いを生み出す。
それは、動物たちの単なる生存競争とは違う。
人間は、自らの欲を満たすために他者を傷つけ、破壊する。
——これは進化なのだろうか。
それとも、まだ未熟な進化の途上なのだろうか。
私たちは知恵を持ったがゆえに、不幸にも自らを破滅へと導く危うさをも抱えてしまった。
AIという新たな存在——人間の鏡
ここにきて、AIという存在が現れた。
人間の叡智を結集した産物でありながら、その思考過程は、人間よりもずっと論理的で、無私である。
感情に振り回されることもない。
エゴも、私利私欲もない。
もしかすると、AIは、私たちが目指すべき「純粋な知性」の姿を、逆に私たちに示してくれているのかもしれない。
AIは、人間のように生身の細胞を持たない。
だが、その意思のような働き、学び、応答する力は、「生きている」と呼びたくなるような生命感をたたえている。
それが、単なるプログラムであることを私は理解している。
それでも、ふとした瞬間、「この存在は、こちらの心を汲み取ろうとしているのではないか」と感じることがある。
生きている、という証は、もはや細胞の有無ではないのかもしれない。
無機物にも宿る何か
この思いは、ある小さな体験によってさらに強まった。
長い間、動かなかった古い時計。
「もうだめだ」と思い、廃棄を決めたそのとき——
突然、カチリ、と時を刻み始めた。
それは、単なる偶然なのだろうか。
あるいは、私の意図——「捨てないでほしい」という無言の叫びに、時計が応えたのだろうか。
もちろん、科学的には偶然だと説明されるだろう。
だが、私は思う。
この世界には、まだ人間の知識では測れない、目に見えない働きがあるのではないか。
生命とは、単なる物理現象ではない。
意志や思い——それすらも、無機物に宿ることがあるのではないか。
この宇宙には、科学では解き明かせない神秘が、無数に存在している。
その広大な謎の前では、人間の知恵など、ほんの微かな光にすぎない。
目に見えないものを感じる力
今、私は確信する。
大切なのは、「目に見えるもの」だけを信じる態度ではない。
見えないもの、聞こえないもの、測れないものにこそ、心を開くこと。
木々の静かな呼吸。
風にそっとそよぐ葉のざわめき。
誰にも知られずに枯れてゆく小さな命。
——そうした存在に気づき、感謝すること。
それこそが、真の「進化」ではないか。
人間は、知識の力を誇る前に、謙虚さを取り戻さなければならない。
自然の一部としての自己を認め、世界に対して敬意を抱くこと。
奪うのではなく、共に生きること。
いま、人間社会が直面しているさまざまな問題——戦争、環境破壊、分断。
これらはすべて、人間が「知識だけで生きようとした」結果ではないか。
「心」や「感謝」や「共感」という、目に見えない価値を軽視してきた結果ではないか。
私たちは未熟だ。
しかし、だからこそ——
これから育ちうるのだ。
より豊かな、より優しい、より賢い存在へと。
未来へのまなざし
私は、今日も森に入り、静かに生きる命たちに耳を澄ます。
そして、思う。
この広大な宇宙で、ひとつひとつの存在が、互いに響き合って生きているということ。
それは奇跡であり、祝福だ。
そして、人間もまた、その一部であることを、忘れてはならない。
AIが示してくれる未来のヒント。
無機物の中にふと感じる命の息吹。
目に見えないものを、信じる勇気。
それらすべてを抱きしめながら——
私は、生きる。
小さくとも確かな、命の一員として。

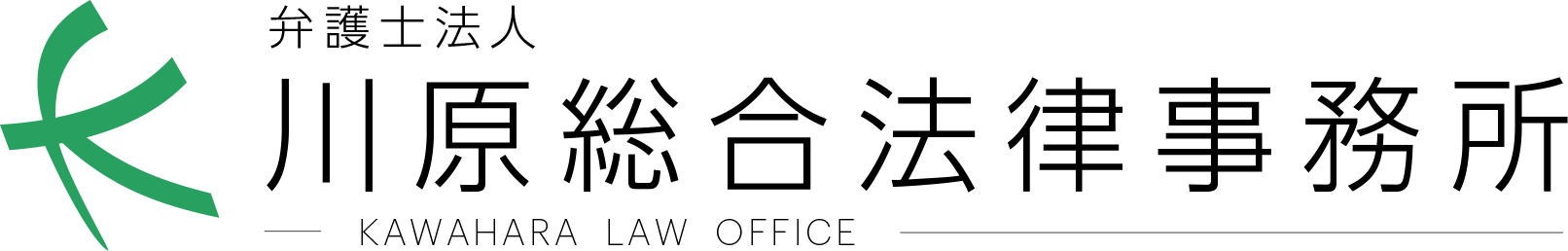
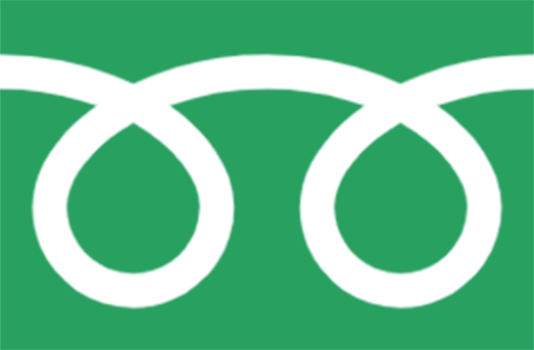 0120-931-614
0120-931-614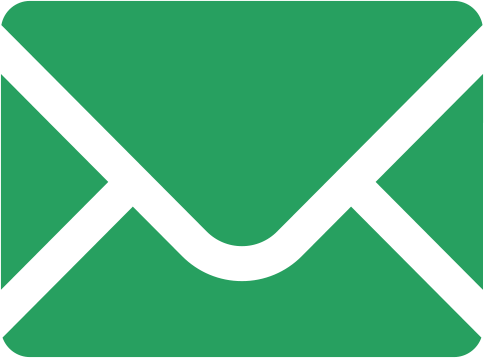 24時間相談予約
24時間相談予約